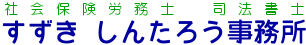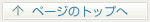不動産の贈与・財産分与・親族間の売買登記申請のほか、適切な契約書の作成も重要
目次 かんたん!司法書士の選びかた
作成する書類も、見積もり時点では未定?
売買であれ贈与であれ、知り合いとの間での不動産の名義変更は方針が決まっていればつぎのような手順をたどります。
- 現在の登記の状況の確認
- 必要な登記申請の確定
- 当事者双方(不動産を譲る側と引き取る側)での契約条件調整・契約書案の作成
- 当事者双方での必要書類と費用や代金の準備
- 契約書ほか登記申請に必要な書類への調印と登記申請
冒頭の1.2.で登記費用の総額が変わる可能性があるのは先に述べたとおりですが、一般の方からのご依頼では3.にも問題が発生します。
失礼ながら大体の方々は、不動産の名義変更について単に所有者として登記されている人物が書き換わって新しい権利証ができればいい、という程度に考えています。
自分で登記をすることを推奨するさまざまなウェブサイトもそうで、必要書類が揃って申請する登記が決まった場合の簡単さにのみ注目して本人申請を推奨しています。
契約書に書けることは案外多いかもしれません他の契約がいいかもしれません
ところが実際には問題は登記申請よりずっと前の段取りにあります。年の途中で不動産を譲渡する場合の固定資産税の負担や、確定測量をせずに土地を売却した場合に土地の実測面積が登記面積と違っていたらどうするか、建物の水回りに故障が発生した場合の修理費用などといった、合意しておけば争わずに済むことについて何も決めないで申請を強行するのは残念ながらよくあることです。
こうしたことは第三者から聞かれないと当事者も気づかないため、そもそも契約書に何を書いたらいいか、契約書を作るかどうかも決まっていない状態で見積もりの依頼が来る、というのもよくあることです。当事者の関係が良好な状態でなされる不動産譲渡、つまり親から子への贈与であれば多少の試行錯誤は問題にならないのかもしれませんが、離婚に伴う財産分与では手続きのやり直しに相手の協力が得られないかもしれません。離婚時には元配偶者ではなく自分の子に不動産を渡したいなど、財産分与の枠組みとは別の契約で対処してもいい・しなければならない案件も見受けられます。
司法書士に不動産名義変更の依頼を出すと言ったとたんに契約書と委任状が司法書士からポンと提示されて、当事者がそれに署名捺印して権利書とお金を渡したら2週間後に不動産の名義が変わる、とは考えないでください。
むしろそうした画一的な対応は、あまり誠実な仕事ではない可能性があります。
特に離婚時の財産分与では契約書(離婚給付契約書)の内容でかなり試行錯誤を要することが多く、当事務所でも最低一回のやり直しを見込んだ見積もりをお出しすることがあります。契約書を丁寧に作ったりやり直しが発生したら費用はどう変わるか、は念のため確認しておくとよいでしょう。その契約書を公正証書にするかどうかによっても、登記費用の総額は数万円変わります。契約事項の一部を公正証書にしないことでさらに費用を調整することもできるでしょう。
契約書を作成する士業
知り合いとの不動産の名義変更では、主に行政書士・司法書士・弁護士が契約書を作成しています。行政書士にも丁寧な契約書を作る人はいるし、弁護士が作成しても当事者が誰かわからない契約書を見たことがあります。契約書作成の費用は弁護士が最も高額になるのが一般的な傾向ですが、商売が上手な行政書士が上手に高めの報酬を取っている、ということもあります。。
契約書作成費用の決め方としては、売買・贈与・離婚などの類型に分けて費用を決めておくもの・枚数に応じて数千円ずつを加えるもの・契約書に記載する権利や義務の金額や項目の数に応じて増加させるものなどがあります。
公証役場では契約書記載の金額に応じて数千円ずつ、ページ数に応じて数百円ずつ費用が変わりますので後者に近く、統一的な報酬額基準があった頃の行政書士・司法書士は枚数に応じて報酬が変わる体系を採っていました。
当事務所では枚数によって費用を決めることが多いのですが、困難な案件では投じた時間数で費用を定めることもあります。
最近、首都圏のある司法書士事務所で「売買価格」に比例した金額で契約書作成の報酬を定めた事務所の見積書を見たことがありました。文案の内容はほぼ市販の売買契約書と同じで、かんたんなアンケートで当事者の意向を聞いてそれにより若干の記載事項を変える、という作業手法を取るようです。仮に不動産の価格1000万円なら契約書作成料10万円、所有権移転登記の報酬は別途、というような形になるのですが、手間と関係ない机上作業で大きく費用が増える点で好感は持てません。
いずれにせよ、契約書を士業に作成させる場合もあらかじめその費用の見積もりを得ることができます。状況にもよりますが、必ずしも士業に依頼しなければならないわけではありません。