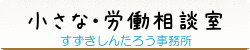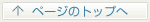推定計算
法的に誤りのない請求をかけるには、正しい権利の把握が必要だ。
個別的労働紛争においてはこれが、実は難しい。残業代の計算は特に、未払期間が伸びるほど煩雑になる。
今回は、社会保険事務所からの照会の直後に放たれる内容証明の送達が実質的な第一撃になるわけだが、ここでおかしな計算をやって催告書と訴状の計算結果が大きく異なるようでは、原告の主張が二転三転していると敵に叩かれても文句が言えなくなってしまう。
それに、今はもう平成13年6月。催告書を放った後は8月末の社会保険労務士の試験勉強を最優先しなければならない。それがおわればもう9月。平成11年9月25日が砂上事務所での第一回目の支払日だったから、文字通りこの催告書をだしたあとは訴訟手続に移行するよりほかなく、万一催告を怠っていた部分があろうものなら法廷で消滅時効の成立を主張されてアウト!だ。
なんのことはない。内容証明送付の時点で、訴状がすでに書けるだけの状態まで権利関係だけは掌握しておけってことじゃないか。オイオイ。
そして情けないことだが、いまだに自分の基本給がいくらだったのかさえ、実は確定してはいないのだ。
なぜなら就職最初の平成11年9月は、基本給18万5千円、その翌月と11月は18万円、12月と翌年1月は18万5千円と変化して、なんの説明もなかったから。
ここから先は法解釈学の世界、ではない。
散らかった史料(『資料』ではない)と関係者たちの記憶や意識の混沌に向けて、労働法という光でいままで見えなかった世界を照らし出す考古学、または当事者間のあらたな規範関係を描き出す法社会学の領域だ。
そう。「おれたちは丁稚」「センセイ様の指示は成文法規に優越する」というのがぼくの昔の法規範。
新しい意味づけをあたえてやるならば「砂上事務所の労働条件は労働基準法違反」「ぼくの請求は、ようやく対等の立場まであがってきた人間(決して丁稚などではない!)の『法律で定められた最低限の』権利行使」。
天動説と地動説ぐらいの違いだが、個別的労働紛争ではよくあることだ。
だが「月給制労働者の割増賃金は労働基準法施行規則第19条1項4号によって計算して払え」という規範意識は、「借りた金は払え」という規範意識ほどメジャーではない。残念ながら、ね!
基本給の推定
言ってしまえば「どれにしようかな、それはカミサマの言うとおり」の世界だ。利害得失を考えてみよう。
18万円にした場合
少なくとも過大な請求にはならない。ただし平成11年9月、12月、平成12年1月に18万5千円もらった理由が説明できないため、やんちゃな弁護士なら過払い金5千円の3ヶ月分を返還せよと言ってくる可能性がある。おまけに計算し直す割増賃金が自動的に減ってしまう。つまり請求できる金額は全体的に減少するうえに、敵からその1割を優に超える額を奪取されかねない。このことを考慮に入れた場合、実は危険な選択肢。
これは採らない。いま僕は、謙譲が美徳な世界にはいない。
事実経過のとおりに、18万円もらっていた月も18万5千円もらっていた月もあった、と認識する場合
おたがいにいい加減だったんだよ昔はね、と認識するもの。実は当時の両者の「感情」に一番沿うという圧倒的利点を持つ。
18万5千円で押し切る場合
いい加減になったのは全部砂上が悪いんだよ!と認識するもの。「労働法の解釈」には一番沿うというおおきな利点を持つ。
これは平成11年10月、11月の基本給が18万円支給されているのを、「契約上は18万5千円支払うべきものを、5千円払ってない状態」と認識するもの。必然的に、敵はここを否定してくる。争点を一つ増やしてしまうことになる。
ただ、かなり強い論拠はある。なにしろ、一番最初の給料である平成11年9月の基本給が18万5千円なのだ。
このことと、「労働契約における賃金を明らかにする義務は、専ら使用者に属する」ことをあわせて考えよう。砂上事務所では賃金を明らかにせず働きはじめたわけだ。それが最初に「明らかになった」のは他でもない。平成11年9月の給与明細をもらったときなのだから、それが賃金の明示だという線で押し切ってしまえばいい。
「ではなぜ平成11年10・11月の給料が安かったことを黙っていたのか?」と聞かれたら、言ってやればいい。「砂上事務所はセンセイの意に染まない『スペア』は叩き出される事務所だったからです。第一、労働者の承諾なくして労働条件の根幹である賃金を不利益に変更することは認められません」と。うまくやれば労働条件の明示義務を怠っていたことはじめ砂上事務所における労務管理のずさんさを、かえってクローズアップできる。だからこの請求は、裁判所に持ち込んでもそれ自体でぼくへの心証が悪くなることはない…だろう。
だからここでは、積極攻勢に出ていい。
ということで全勤務期間にわたって18万5千円の基本給の『はずだった』という主張を展開することにする。つまり平成11年10・11月は基本給の未払5千円の2ヶ月分1万円がある、ということ。
ここでもし平成11年9月の、いわば初任給が18万円だったらこんなことはしないが、自ら弱みを作った砂上が悪いのだ。
退社に伴う基本給
とにかく基本給は、月給18万5千円で押し切ることに決めた。
次は2月に中途で離職したことで、賃金が時給で支払われている点をどうするか、だ。こうした場合の処理に関しては規定がない。
ただし大事なことは、月の途中で辞めたからといって労働時間あたりの賃金が減るようなことは絶対あってはならない、という点だ。これも一種の労働条件不利益変更になるから、労働者の承諾がなければこんなマネできはしない。
じゃあどうすればいい?
要は、スジがとおっていればいい。
まず考えたのが、割増賃金を算定する時に使う労働基準法施行規則第19条に従って計算した、「通常の労働時間の賃金」をそのまま使うということだ。これは1252円82銭になる。
こっちが100円以上高いから、採用したくなるが…論拠がちと弱い。
ここでの弱みは、あくまでも同条は『割増賃金の算出のため』に通常の労働時間を算出しているものだ、と言う点である。通常の労働時間の算出そのものは、直接の目的ではないのだ。しかも同条の立法趣旨そのものが、毎月毎月カレンダーに従って所定労働時間は変化するが、月給は変わらないという状況を素直に受け入れた上で「毎月変わる所定労働時間で割増賃金を毎月計算し直す必要はないよ。年間の平均を決めて、それを1年間使ってもいいことにするよ」というものにすぎない。労働者の権利を強化する、というよりは、計算の便法を定めたものにみえる。
次に考えたのが、この月の所定労働時間と解雇までに働いた所定労働時間で、月給を案分することだ。
つまり平成12年の2月3日を含む給料計算期間(砂上事務所では平成12年1月26日から平成12年2月25日)における、所定内労働時間をカレンダーに従って163時間と算出し、実際に勤務した所定内の時間をαとして、185000÷163×αとするもの。これなら過不足が生じない。
ちなみにこの考え方を使うと、この期間の所定内労働時間1時間の賃金単価は185000÷163=1134円96銭になる。実情に沿っていて、問題はない。ただし、前者より安い。おまけに、ただでさえごちゃごちゃと計算を並べなければならないところへまた計算を増やすことになる。訴状のページ数が増える。どうしよう。
砂上事務所の1年間の所定の、というより名目上の所定労働時間は、盆暮れ休みや祝日のおかげで、平成12年は1772時間だ。月平均で、147.7時間。一方、ここで問題の1月26日から2月25日まで、というのは祝日は1日しかないうえ、期間としては31日間もあるおかげでこの賃金計算期間は、所定内の労働時間が163時間となり、月平均147.7時間より顕著に長くなってしまう。
この点を事実に即して真っ正面から突かれたら負ける可能性が高い。ここでは、「1年の平均」より「1ヶ月の、所定労働時間での案分」を採用しよう。当月分の割増賃金もそれにあわせておくことにする。
賃金単価
今年と来年とで月給は同じ人でも、時間外労働割増賃金額は変わる。
素直に法律を読めば、そうだ。
これを読んで残業代請求事案を(幸か不幸か)ぼく以外の法律関係者に依頼しようとするならば、さりげなく試してやればいいだろう。
その人が「年をまたがって」数ヶ月間の割増賃金を同じに計算するか否かを。
躊躇することなくその年々のカレンダーを引っ張り出してくるなら、なかなかの人ということになる。
なぜそんなことになるのか。
そもそも時間外労働をはじめとする割増賃金の算定に当たって用いるべき「通常の労働時間の賃金」の算出方法は労働基準法施行規則第19条各項に定められている。同条第1項第4号では『1年間における1月平均所定労働時間数』で、月給額を割って通常の労働時間の賃金を計算しなさいよ、とうたっている。
入力すべきパラメータのうち、月給額はかわらない、としよう。
でも「1年」には365日の年も366日の年もある。2月29日が平日か日曜日か、で一年間の所定労働時間は変わるし、365日の年でも、52週間は364日。残りの1日が土曜日になる年も火曜日になる年もあるし、振り替え休日が多い年も少ない年もあるではないか!
そもそも「1年」っていつからいつまでなんだ、というもっと根元的な問いにさえ直面する。この場合当事者で別段の定めがないなら、暦年でいいという通達が出ている。だから平成11年8月から翌年2月まで在職したぼくの場合も、平成11年分と平成12年分の請求では、割増賃金の計算を分けている。
さらに、こうした割り算で必然的に発生する「円未満の取扱い」については通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第二条第二項に、計算単位として銭、厘まで使うとある。そして、たとえば訴訟上相手に支払を求める際には同法第三条第一項により(厘まで使って計算した)合計額について、50銭以上なら切り上げ、未満なら切り捨てをしてやればいいそうな。ただぼくは面倒なので、銭未満の単位は常に切り捨てた。
これは権利を放棄することになるだけなので訴訟の勝敗に与える実害はないし、ちゃんと説明できてやり方が一貫していればそのように訴状に書いたって、なんの問題もない。
で、実際にカレンダーをプリントアウトし、おもむろに休日をボールペンでチェックする。これとにらめっこしながら必死で平日と休日と、砂上事務所では土曜日の勤務時間は3時間なので出勤する土曜日の数を数えていく。在職中にお盆休みが8月13日から16日まであったと聞いていたので、それはもちろん所定休日だ。
その結果、平成11年の所定内労働時間の合計は1754時間、平成12年は1772時間となった。
これで基本給を割ってやって、通常の労働時間の賃金は平成11年が1265円67銭、平成12年が1252円82銭、残業代=時間外労働割増賃金はそれぞれ1.25倍して、1582円9銭、1566円2銭が正解だ!だいたいの推定で1500円行くだろうと思ってはいたが、まさかこれだけのものになろうとは!と一瞬喜んだ。
しかし同時に自分が無知だったことの重さに気づいて、慄然とさせられる。
法内残業対『違法残業』
手持ちの給与明細によれば、この労働契約で『早出残業手当』として計上されているのは、平成12年1月25日までで合計231時間19分。2月3日までの分は基本給部分と一緒にして時給千円で計算されているため、今はわからない。
ではこの231時間19分に、さきに計算した千五百数十円なりをかけていいのか、といえば…そうでない。
なぜなら砂上事務所の平日の所定労働時間は、『7時間』だから。
労働基準法第32条では週の法定労働時間は40時間、1日では8時間…これは常識だが、この1日8時間と7時間のあいだの「法定内ではあるが、当初の労働契約時間外」の残業については労働基準法所定の割増賃金を支払う必要は『ない』。この場合は通常の労働時間の賃金を払えばよいことになっている。
労働基準法の規制に触れない残業だから、「法内残業」というわけだ。さりとて砂上事務所のように、時給千円などとぬかした場合は残業させた時間の方が通常の労働時間より安い(!)賃金になってしまう。これはナンセンスなので、当然差額の支払いは求めていい。
砂上事務所で平成11年の平日1日、9時から20時まで働いたとする。
まず9時から17時までは、完全に所定内。基本給18万5千円の範囲だ。ここでまず、7時間働いている。
17時から18時までは、労働契約上は所定時間外になる。ただし労働基準法上、1日あたりの労働時間の規制の中にはある。これは法内残業。砂上さんは時間1000円払っているが、本来なら1265円67銭が正解。よって差額の未払分、1時間あたり265円67銭請求できる。
18時以降20時までは1日8時間を超えているから、間違いなく法定外の時間外労働になる。よってこの部分は時間外労働割増賃金である1582円9銭払わねばならないので、差額1時間あたり582円9銭請求できる。
それに法定外の時間外労働させることそれ自体、労働基準法第36条の労使協定を締結し届け出なければならず、適正な割増賃金の支払いも36協定の締結もないこの『残業』を違法残業と…この訴訟の上では呼ぶことにした。普通は法外残業というのだろうが、ここは違法性を強調するだけした方が裁判官の心証を有利にできそうな気がする。
さらに平日17時から18時の残業だが、常に法内残業ということにはならない。ここが労働基準法のありがたくも複雑なところだ。つまり、1日の労働時間の規制には収まっているようにみえても、1週間の労働時間の規制からはみ出ていればそれが違法残業になるからだ。
具体的には砂上事務所の場合「月曜日から金曜日までと、土曜日の合計6日出勤する週」で、一部の17時から18時までの残業が違法残業になる。
なぜなら月曜から金曜までで、すでに所定内労働時間は7×5=35時間。これに土曜日3時間で合計38時間、所定内で勤務しているから。したがって月曜日と火曜日については、まだ(週40時間の規制まで)2時間残っているため18時までの1時間ずつの残業は法内残業になる。
水曜から金曜までの残業は、もうだめだ。火曜日の法内残業が終わった時点で、法定内の労働時間である一週間40時間の枠からはみ出ることになってしまう。よって水曜から金曜の、17時から18時までの残業は、この週にかぎって違法残業になる。
これでやらなければならないことは見えてきた。まず各月で「週38時間働いてしまう週」と「そうでない週」をわけて、さらに各週の各日の17時から18時までの残業について、38時間働いてしまう週では法内残業にあたるか違法残業にあたるか分けてやればいい。
煩雑だが、これが『正解』だ。難しいのではない、煩雑なだけだ。やるべきことは、はっきりと見えた。
これこそが、法と裁判制度の雲間から、労働あって労働法なき行政書士事務所の闇を照らすまっすぐなひかりの帯-天使の梯子-なのだ。
あとはこの天使の梯子を一歩一歩、労働基準法言うところの「最低の」基準へと、あがっていったらいい。
それは確かに最低の基準、というけれど、昔の自分はそのずっと下の闇の中にいたのだから。
残業時間の推定
…とか、言っちゃあみたけれど。
実はタイムカードは手元にないのだ。だから退社時間は把握できない。
さらに砂上事務所の給与明細は法内残業分も違法残業分も、とにかく17時過ぎの就労に関しては一緒くたに把握して計上してあるだけ。実は手持ちの資料では、分離のしようがないんだよな、と。
こまったもんだ。こんなもののために証拠保全の申し立て、なんて通るはずないし、労働基準監督署も使えない。「労働時間の再集計のためタイムカードを見せてください」なんて言った日にゃ、砂上の奴なら即刻焼却処分にかけるに決まってる。なにしろあいつには順法精神はまるでない。
適当に訴訟を起こしておいて文書提出命令をかけるか?…ナンセンス。債権額を確定しないのに、どうやって訴訟をおこせというんだ?
そんなもんテキトーに見積もるかでっちあげるかすれば…
はて?適当に、じゃなくて、『適切に』なら、訴訟は維持できるんじゃないか?
ぼくの頭の中はだいたいこんな風に動いている。負荷がかかりすぎると独り言という形で、思考過程が外部に漏洩する。砂上事務所で測量計算なんかやっていた頃は、一人で賑やかに交点計算だの平行移動だのやって、蓮江さんや笹金さんに気味悪がられていたこともあったっけ。
独り言の嵐が去った後、たどり着いた結論はこうだ。
砂上事務所の給与明細に提示されているのは「法内残業時間」と「違法残業時間」の合計だ。双方は分離されていない。
そして法内残業時間はその性質上、1日または1週間での規制があって上限が決まっているのだから…
一時間あたりの賃金額が少ない、「法内残業時間」の、理論上の最大値をカレンダーから算定して、残った残業時間は「違法残業時間」と認識すればいい。そうすれば裁判上の請求額としては常に最小の額を請求するものになるから、たとえ実際の毎日の退勤時間がわからなくても、これで訴訟を維持して構わないはず!
たとえば平成11年9月の給与明細によれば、残業時間は40時間44分。この中に、法内残業時間と違法残業時間が入っているが、内訳はわからない。だからいろいろな可能性を考えてみよう。
まず、週6日出勤する一週間に含まれる3日間で40時間44分残業して、あとの各出勤日は定時退勤した場合。
法内残業時間は2時間で、違法残業時間は38時間44分。これが法内残業時間の、理論上の最小値。単価の高い違法残業時間の最大値だから、請求額も最大になる。
では最小値は?これは、各出勤日に残業が散らばった場合が、違法残業の時間数が最小になる。土曜日出勤しない週ならば、1出勤日に1時間は、法内残業ができるのだから。
そして土曜日に残っても残業時間をつけたことはほとんどないから、いまは月曜日から金曜日のことだけ考えればいい。
これでいい。請求額としては推定に基づく額になるものの、最低の額を推定しているだけだから問題ない、という線で押し通す。
またカレンダーとにらめっこだ。土曜日出勤のある週は、所定内で38時間勤務するから、法内残業は2時間、月曜から金曜まで出勤の週は所定内で35時間、法内残業は5時間、月曜日に休みがある週は、法内残業ができる日が火曜から金曜までしかないから4時間…と書き出していく。平成12年2月の、57時間の勤務についても同様に処理する。これで各月について、法内残業時間(の、理論上の最大値)と違法残業時間を分離できた。この結果、各月のそれぞれの残業時間は
| 就労期間 | 残業時間数 | |
|---|---|---|
| 平成11年09月 | 法内15時間 | 違法25時間44分 |
| 平成11年10月 | 法内17時間 | 違法36時間20分 |
| 平成11年11月 | 法内15時間 | 違法39時間47分 |
| 平成11年12月 | 法内14時間 | 違法32時間40分 |
| 平成12年01月 | 法内14時間 | 違法21時間48分 |
| 平成12年02月 | 法内02時間 | 違法10時間00分 |
これに単価をかけてやればいい、というわけではないところが残業代支払い請求の恐ろしいところだ。
なぜか。給与の計算期間が、砂上事務所の場合は「毎月26日から25日まで」だからだ。よって平成12年1月支給の給料明細というのは、「平成11年12月26日から平成12年1月25日」の勤務の分なのだが、あくまで当事者になんの合意もない以上、この期間にまざっているはずの平成11年における勤務に対する割増賃金の単価と平成12年における割増賃金の単価で区別してやるのがスジになる…が。
どうしよう?面倒だ。また訴状が厚くなる。
ということで、またも権利の過少行使に逃げることにする。
具体的には平成12年の方が賃金単価が低いから、平成11年12月26日以降はすべて、『低い賃金単価の方で』算定したと訴状には書いておく。
これで割増賃金については、あとは単純にかけ算して合計するだけだ。やれやれ。
賞与の計算
どうせこれは、内容証明に景気づけに記載するだけだ。ただしこれで話がもつれて支給状況が明らかになってくるなら、やはり砂上事務所の労務管理のずさんさが見えてくるはず、という狙いは当然ある。求人公開カードによれば年4ヶ月分、ということは1年勤め上げれば18万5千円×4=74万円。
これを入社から退社までの総日数157日で案分してやって、74万÷366日×157日=31万7432円。このうち10万円は支給されているので、差額21万7432円を、一応請求することにする。
なお、提訴後に被告側から提出された証拠では、平成11年12月に支給されたこの賞与について、平成11年8月末採用のぼくと、同年2月採用の蓮江さんとで同額の「10万円」だった。
このことは賞与の支給に当たって在職年限はあまり考慮されていないことを意味する。また、
平成12年9月および平成13年6月に入手した砂上事務所の求人公開カードでは、いずれも「前年度賞与 年2回 計4.0ヶ月分」とされている。
一般に求人公開カードの内容はそのまま労働契約の内容にはならない。だから、ぼくが就職した平成11年8月の求人公開カードのみを根拠にこの「4ヶ月分の賞与」を請求することは非常識だ。ぼくでもやらない。ただ、「前年度の実績として、支給した」と書いてある平成12年と翌年の求人公開カードを添付してやった場合、それは、本当に平成11年の賞与支払い状況を立証するものになりうる。ここを叩いた場合、砂上はかなり苦しい立場に立たされただろう。
解雇予告手当の計算
実はここまでの計算が出来ていないと、解雇予告手当の額が決まらない。
なぜなら平均賃金の中には、当然に残業代が含まれるためだ。
解雇予告手当としては、解雇言い渡しの日が平成12年2月2日、解雇の日が翌3日。よって平均賃金の29日分を請求できることになる。その平均賃金の計算期間としては、直近の給料支払い締め切り日まえ3ヶ月だから、平成11年10月26日~平成12年1月25日までの「適正な残業代が支払われたものとして計算した」解雇予告手当を請求するのがスジである。
前々項まで頑張って推定作業を繰り返したおかげで、この期間に本来支払われるべき残業代込みの賃金の総額は、78万6606円となった。
これを、この期間92日で割ってやって平均賃金は786606÷92=8550円。この29日ぶんで、8550円×29日=24万7950円。
ちなみにこの期間の給料として、既に支払われている金額は69万7249円である。この金額から安直に解雇予告手当を出すと21万9785円。黙っていれば3万円弱安い額に甘んじなければならないところだ。
つまり、司法書士に書類作成を依頼した場合の報酬ぐらいは出てしまうのである。少なくともいまのぼくの事務所では、そうだ。
このコンテンツは、ブラックな零細企業の残業代不払いと本人訴訟の体験談です
給料未払い解決のための相談と法的手続き・これらの費用に関する情報は
賃金・残業代・解雇予告手当の請求に関する内容証明郵便の作成方法は